法定点検と車検の違いとは?検査項目や費用、受けなかったときの罰則?

新車・中古車に限らず、安全に走るためには所有する車の法定点検(定期点検)を実施する義務があります。しかし、費用や頻度まで詳しく把握している方は少ないかもしれません。
そこでこの記事では、法定点検の概要を踏まえながら、費用や頻度を詳しく解説します。法定点検についてしっかりと押さえておくことで、車を安全に使用できるでしょう。車種別に詳しい点検項目や主な依頼先も紹介します。
※目次※
・法定点検と車検は別物で、点検内容や実施時期が異なる。
・車検の場合は有効期間を過ぎると罰則の対象だが、法定点検については規定されていない。
・法定点検はディーラーや整備工場、カー用品店などさまざまなお店に依頼できる。
法定点検と車検の違いを理解しよう

「法定点検と車検の違いが分からない」という方もいるかもしれません。法定点検と車検は別物であり、目的や定義が全く異なるので違いを把握しておくことが大切です。ここでは、法定点検と車検のそれぞれの概要を解説します。
法定点検とは
車の安全走行維持が目的の整備点検を、法定点検といいます。法定点検を実施すれば、車が持つ性能を維持でき、整備不足により起きるトラブルを防ぐことにもなるでしょう。
道路運送車両法第48条(定期点検整備)では車の使用者に対し、法定点検を実施する義務を定めています。12か月点検、24か月点検、3か月点検、半年点検の4種類があり、車種によって周期や点検内容が異なることを押さえておく必要があります。
自身が使用する車はどの法定点検をする必要があるのか、正確に把握しておきましょう。以下が主な車種ごとの点検頻度です。
・乗用車・軽自動車(自家用車):12か月点検・24か月点検
・事業用車(タクシー・バスなど):3か月点検・半年点検・12か月点検
車検とは
車検は自動車検査登録制度の略です。点検ではなく、国が実施する検査であることが法定点検との違いのひとつといえるでしょう。以下に「目的」という観点での法定点検と車検の違いをまとめました。
・法定点検の目的:安全かつ快適に車を使用する(トラブルや故障の防止)
・車検の目的:法律(道路運送車両法)が定めた保安基準をクリアしているかの検査
車検は、使用する車の基本となる項目(構造や乗車定員、公害防止など)に問題がないかを検査する制度といえます。問題があれば修理をしてクリアすれば通過可能です。トラブル防止の観点から、車検だけでは車の状態を良好に保つのは難しいといえるでしょう。
なお、乗用車・軽自動車(自家用車)かつ新車の場合は、新車登録から3年後に新規検査を受けます。それ以降は継続検査になるため、2年に1回のペースです。
次の車検との間に12か月点検がある意味は、大きいといえるでしょう。また、法定点検である24か月点検は、車検に合わせて受けるのが一般的です。
法定点検の実施時期はいつ?

法定点検は、車の種類によって実施する時期が異なります。「車の法定点検はいつ行うのだろう」と疑問に思っている方も多いでしょう。法定点検を受けないと、罰則を受けるケースもあるため、注意が必要です。
ここでは、車の法定点検を受ける頻度やタイミング、点検を行わなかった場合の罰則について解説します。
車の種類別に見る法定点検のタイミング
車の種類によって、法定点検の頻度も異なることをご存じでしょうか。点検頻度は安全走行のためにも正確に把握しましょう。
|
車の種類 |
頻度 |
|
乗用車・軽自動車(自家用車) |
12か月に1回・24か月に1回 |
|
中小型トラック(自家用車) |
6か月に1回・12か月に1回 |
|
バス・トラック・タクシー(事業用車) |
3か月に1回・12か月に1回 |
|
レンタカー(乗用車) |
6か月に1回・12か月に1回 |
|
レンタカー(乗用車以外) |
3か月に1回・12か月に1回 |
|
大型トラック(自家用車) |
3か月に1回・12か月に1回 |
|
二輪自動車 |
12か月に1回・24か月に1回 |
(2024年7月時点の情報です)
対象車種によって点検周期が異なるだけでなく、点検項目数も異なります。例えば自家用車の点検項目は12か月点検では29項目ですが、レンタカー(乗用車)は86項目です。
車の用途や種類によって頻度や項目数を適切に設定し、車の安全性を高めて事故防止を目指していると考えられます。
法定点検を受けない場合の罰則
法定点検に関しては、受けなくても罰則があるわけではありません。道路運送車両法の第48条では、使用者に対して定期点検の実施を義務付けていますが、罰則に関しては規定されていません。(一部事業者は除く)
ただし、車検に関しては罰則が設けられている点に注意が必要です。自動車検査証(車検証)の有効期間が過ぎている状態で運行すると、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課せられます。車検を業者に依頼すると、24か月の法定点検を同時に実施することがほとんどです。
法定点検を実施する際の適切なタイミング
一般の乗用車における法定点検は、1年ごとに受ける必要があります。24か月点検であれば車検と同時並行で実施しますが、12か月点検は点検ステッカーを参考に実施するのが一般的です。
点検ステッカーはフロントガラスの左上に貼られることが多い、丸い形状のシールです。外側には12か月点検の年月が分かりやすく表示されています。
また、点検ステッカーの裏側にも次回の点検をいつまでに実施すべきか記載されているので、一度確認してみてください。
法定点検を実施するメリット
自動車は便利ですが、走行には危険が伴うため安全性を確保することが大切です。法定点検を実施すると、パーツの劣化などの不具合に気付けるため、トラブルの予防につながります。
ブレーキの残量やハブベアリングの劣化など、走行に関わる重要な部分の状態が分かり、必要に応じて整備することでより安心して運転できるでしょう。
またメーカー保証がある場合は、法定点検で保証対象部品に不具合が見つかった場合、無償で修理できます。他にも車を売却する際の査定で、プラスに働く可能性があるでしょう。
法定点検はどこで受けるのがベスト?

法定点検を実施する時期が近づいたら、どこで受けられるのかを確認しましょう。法定点検は、ディーラーや整備工場、ガソリンスタンドなどの業者に依頼するのが一般的です。ここでは、法定点検の主な依頼先と、それぞれの特徴を解説します。
1.ディーラー
ディーラーとは、特定の自動車メーカーの新車を販売している業者のことです。ディーラーでは車の購入だけでなく、法定点検を含めさまざまな整備を依頼できます。ディーラーでは取り扱う車種の特徴を把握しており、専門性や品質の高さが魅力です。
また、メーカー保証期間内の法定点検で対象部品に不具合が見つかった場合、そのまま保証を使用して修理してくれるでしょう。
2.ガソリンスタンド
ガソリンスタンドの多くの店舗では、給油以外にも洗車やオイル交換などのメンテナンスを実施しています。また、敷地内に整備工場を完備している場合があり、法定点検を依頼できるケースもあるでしょう。利便性の高さがガソリンスタンドの特徴です。
近場に法定点検を実施しているガソリンスタンドがある場合は、料金を確認しつつ依頼を検討してみてください。
3.整備工場
地域によっては、個人もしくは地元の企業が運営している整備工場があります。修理で利用したことがある方もいるでしょう。これらの整備工場でも法定点検を依頼できる場合がほとんどです。
さまざまな車種に対応していることが多く、部品の在庫を持っていることがあるため、整備が必要になった場合でもスムーズに対応してくれるでしょう。
4.車検専門店
車検を専門に実施している整備工場があります。このような車検専門店でも、法定点検に対応していることがほとんどです。車検専門店はスピーディーに車検を進めるため、システム化していることもあり、法定点検においても素早く実施してくれるでしょう。
点検費用は比較的リーズナブルな傾向があります。ただし、料金設定はお店によって異なるので、事前に確認することが大切です。
5.カー用品店
カー用品店では、車を便利かつ快適に使用するためのアイテムを豊富に販売しています。また、タイヤ交換やバッテリー交換、オイル交換などのメンテナンスに対応しているのも特徴のひとつです。
車検や法定点検を依頼できる場合もあるので、まずは問い合わせてみてください。カー用品店に法定点検を依頼すると、消耗品の交換費用を安く抑えられる可能性が高いといえます。
車の法定点検の種類と検査項目

法定点検は、点検の種類ごとに項目が定められていることが特徴です。ここでは、それぞれの法定点検の内容と対象車種を詳しく解説します。実際に点検する項目を把握して、法定点検に対する知識を深めましょう。点検に要する時間も目安として紹介しています。
法定1年点検(12か月点検)
乗用車・軽自動車(自家用車)の12か月点検は、メーカー保証を受けられるケースも多くあります。所要時間は1時間前後が目安です。
業者に依頼した場合は状況によって変わります。事前に問い合わせておきましょう。12か月点検の点検箇所と対象車種、点検項目数を以下にまとめました。
【12か月点検】
|
点検箇所 |
主な点検箇所 |
|
走行装置 |
・ホイール |
|
かじ取り装置(ステアリング) |
・パワーステアリング装置 |
|
制動装置 |
・ブレーキペダル ・パーキングブレーキ ・ホース及びパイプ など |
|
動力伝達装置 |
・クラッチ ・トランスミッション、トランスファー など |
|
電気装置 |
・点火装置 ・バッテリー |
|
原動機 |
・本体 ・潤滑装置 ・冷却装置 |
|
エグゾーストパイプ・プマフラー |
※前回の点検(または車検)以降の走行距離が5,000km以下の場合は省略可能 |
(2024年7月時点の情報です)
【対象車種・点検項目】
|
車種 |
項目数 |
|
乗用車・軽自動車(自家用車) |
29項目 |
|
中小型トラック(自家用車) |
86項目 |
|
大型トラック(自家用車) |
101項目 |
|
レンタカー(乗用車) |
86項目 |
|
レンタカー(乗用車以外) |
101項目 |
|
事業用車(タクシー、トラック、バス) |
101項目 |
(2024年7月時点の情報です)
法定2年点検(24か月点検)
車検とセットで行うことが多いのが24か月点検です。所要時間は、車検と同時に実施される場合が一般的なため、業者により異なります。12か月点検と比較すると点検項目が多いため、長くなると考えたほうがよいでしょう。
12か月点検をベースに以下の点検項目を追加します。12か月点検とほぼ変わらない項目もあるため、点検項目は増えますが全く異なる項目を点検するわけではありません。
対象車種は乗用車・軽自動車(自家用車)であり、点検項目は60項目です。追加される項目を中心にまとめました。
【24か月点検:主な点検箇所】
|
点検箇所 |
主な点検箇所 |
|
走行装置 |
・フロント・ホイール ・リア・ホイール |
|
かじ取り装置(ステアリング) |
・ハンドル ・ギア・ボックス ・かじ取り車輪 など |
|
緩衝装置 |
・取り付け部及び連結部 ・ショックアブソーバ |
|
動力伝達装置 |
・プロペラ・シャフト及びドライブシャフト ・デファレンシャル など |
|
原動機 |
・電気配線 ・点火装置 など |
|
ガス発散防止装置 |
・燃料蒸発ガス排出抑止装置 ・一酸化炭素等発散防止装置 など |
|
エグゾーストパイプ・マフラー |
|
|
車体 |
|
(2024年7月時点の情報です)
法定3か月点検(3か月点検)
対象車種は、自家用車ではなく事業用車です。基本的に、法定点検は事業用車のメンテナンスなどの責任を負う担当者が決めた規定に基づき行われます。
整備管理者制度の違反や、法定点検を実施しなかった場合は道路運送車両法第110条に対する違反となることを知っておきましょう。30万円以下の罰金を支払うことになります。以下に点検箇所と対象車種、点検項目数をまとめました。
【3か月点検:主な点検箇所】
・かじ取り装置
・制動装置
・走行装置
・緩衝装置
・動力伝達装置
・電気装置
・原動機
・エグゾーストパイプ・マフラー
・エア・コンプレッサ
・高圧ガスを燃料とする燃料装置など
・車枠及び車体
・スペアタイヤなど:車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の車両が対象
【点検項目数】
|
事業用車(タクシー、トラック、バス) |
51項目 |
|
大型トラック(自家用車) |
51項目 |
|
レンタカー(乗用車以外) |
51項目 |
|
被牽引自動車 |
23項目 |
(2024年7月時点の情報です)
法定6か月点検(半年点検)
さまざまな人が使用する車は、自家用車よりも法定点検の頻度が高く設定されています。レンタカー(乗用車)、中小型トラック(自家用車)が対象車種です。どちらの車種も点検項目数は24項目となっています。半年点検の項目を以下にまとめました。
【半年点検:主な点検箇所】
・かじ取り装置
・制動装置
・走行装置
・動力伝達装置
・原動機
・電気装置など
(2024年7月時点の情報です)
法定点検は自分で行うことも可能?

法定点検を自分自身でできないか気になった方もいるでしょう。ここでは、法定点検を自分で実施する際の注意点と、プロへ依頼するメリットについて解説します。これらの内容を押さえつつ、自分で実施すべきかどうかを検討してみてください。
自分で法定点検を実施する場合の注意点
日常点検は、ライトの点灯状態やタイヤの状態を確認するなど、簡易的な点検項目なので多くの方が実施できるでしょう。
一方で、ブレーキやサスペンションなど普段目にすることがない部分をチェックする法定点検は、専門的な知識がないと良しあしの判断が難しいといえます。
また、新しく張り替える点検ステッカーを手に入れることは難しく、点検整備記録簿の記入にも知識が必要です。作業中のけがや事故の危険性があることも押さえておきましょう。
法定点検をプロに任せるメリット
法定点検は、プロに依頼する方がほとんどでしょう。プロは整備で使用する工具が充実しており、車両リフトを備えた作業場を有するなど、整った環境の中で作業するためスピーディーに点検ができます。
また、専門知識と経験により、交換したほうがよい部分について判断ができるため、適切に整備ができる点も特徴です。さらに、点検ステッカーの張り替えや点検整備記録簿の記載もしっかりと実施してくれるメリットがあります。
法定点検に必要な書類と費用の目安
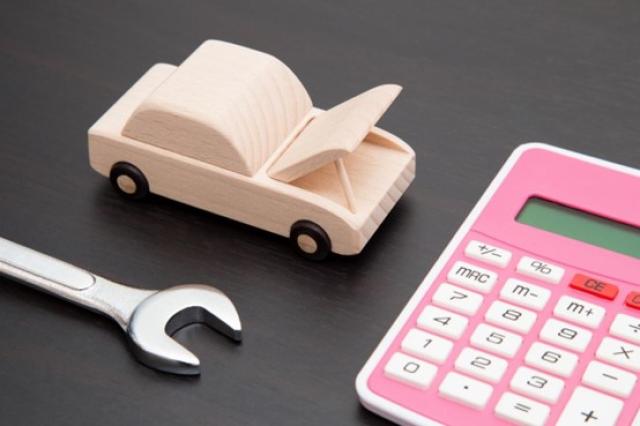
車の法定点検を依頼する場合は、「車検証」と「点検費用」が必要です。費用に関しては、「どの車を点検するか」「どの業者に依頼するか」によって金額が異なることを押さえておきましょう。
ここでは、車の法定点検を受けるときに必要なものと、費用相場について解説します。
法定点検を受ける際の必要書類
法定点検に必要なものは、「車検証」と「点検費用」です。ただし法定点検は、車検と同時に受けるケースもあり、状況に応じて必要なものが変わってきます。
車検と並行して受ける場合は、「自動車税納税証明書」「自賠責保険証」が欠かせません。さらにロックナットなど、特定の部品を使用している場合は、ロックナットアダプターが必要です。
また点検整備記録簿も、あれば提出しましょう。点検内容が細かく記録されるため、売却時などに有利になります。
法定点検にかかる費用の目安
法定点検にかかる費用は、車の種類や依頼する業者によって大きく異なります。例えば軽自動車を点検するのと、2,000cc~3,000ccクラスの車を見るのとでは、大きな違いが出てくるので注意しましょう。
またディーラーや整備工場、ガソリンスタンドなど、業者ごとに費用相場が異なります。金額の目安としては、数千円から数万円です。価格幅が広いので、気になる業者があれば、複数の見積もりを取っておくとよいでしょう。
まとめ

乗用車や軽自動車に関わらず、車の使用者には法定点検が義務付けられています。法定点検のタイミングは自動車の種類によって異なっており、一般的な自家用乗用車の場合は12か月点検と24か月点検を受けなければなりません。
法定点検は自分でも実施できますが、プロに依頼するのが安心です。ディーラーや整備工場、ガソリンスタンドなど、依頼先が近場にないか探してみてください。費用はお店によって異なるので、事前に確認することをおすすめします。
▼ライタープロフィール

小波津健吾
高山自動車短期大学を卒業とともに国家2級整備士資格を取得。その後、整備士として実務経験を積み重ね自動車検査員資格を取り、民間工場で検査員として従事した経歴を持つ。現在はメカニックや検査員の知識と経験を活かし、主に車系のメディアで執筆している。
豊富なラインアップのネクステージ中古車情報をチェック!
いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。
ネクステージでは、他店に負けない数多くの中古車をラインアップしていますので、中古車の購入を検討されている方は、ネクステージの公式Webサイト上で最新の在庫状況をチェックしてみてください。また中古車購入に際して、ネクステージ独自の保証もご準備しております。お気軽にお問い合わせください。


