車検証の見方や有効期限の確認方法は?電子車検証についても解説

車が公道を走行するためには、車検を受ける義務があります。車検に合格すると車検証を受け取れますが、車検証には有効期限などさまざまな情報が記載されているため、どのような見方をすればよいのか分からない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、車検証の基本的な見方、車検証の使用シーン、紛失時の対処方法を紹介します。この記事を読むことで、車検証の記載内容だけでなく、重要性も理解できるでしょう。
※目次※
3.有効期限切れに注意!見方が分かった車検証を使うタイミング
・車検証にはAタイプとBタイプの他に、ICタグ内蔵の電子車検証もある。
・電子車検証には車検の有効期限が記載されていないため、有効期限を確認するにはICタグの読み取りが必要。
・車検証は重要な書類のため、保管場所や保管方法に注意しよう。
有効期限が定められた車検証には2種類のタイプがある
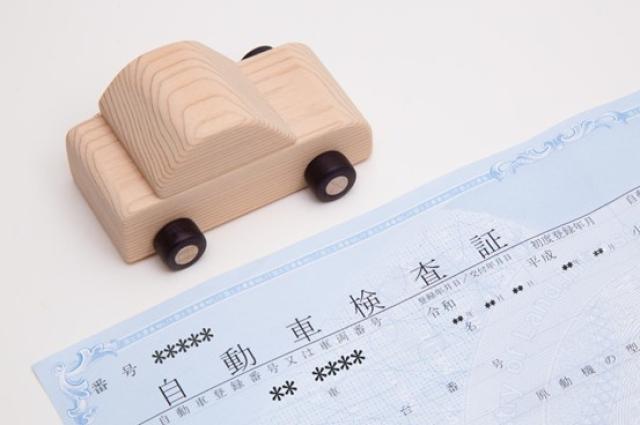
車検証にはAタイプとBタイプがあります。どちらのタイプを持っているかは、車検証左上に印字される英字を見て確認可能です。
また、これまでA4サイズの車検証が一般的でしたが、2023年1月からは電子車検証も登場しました。ここでは、車検証の種類と、これから普及する電子車検証の概要を紹介します。
Aタイプの車検証とは?
Aタイプの車検証は一般的な車検証です。A4サイズの紙に自動車登録番号(ナンバープレート番号)や車名、型式、所有者の氏名住所、使用者の氏名住所などさまざまな情報が書かれています。
所有者情報と使用者情報が同じである場合、使用者の欄には「***」と記載されるのが特徴です。
普通車と軽自動車では、所有者情報と使用者情報が逆に記載されています。また、軽自動車にはAタイプとBタイプの区別がなく、ナンバープレート番号を車両番号と呼ぶのが異なる点です。
Bタイプの車検証とは?
Bタイプの車検証は、車を大量に所有する法人向けの車検証です。Aタイプの車検証と異なり、所有者名や所有者住所の欄がありません。その代わりに、備考欄に所有者情報が記載されています。
Aタイプの車検証は所有者に変更があった場合には、手続きが必要です。そのため、大量に車を所有するリース会社などが手続きの手間を省けるよう、変更手続きが要らないBタイプの車検証が誕生しました。
備考欄に記された所有者情報は車検証発行時の情報のため、最新ではない可能性があることを覚えておきましょう。
2023年1月より電子車検証が登場
電子車検証は、従来の車検証よりもサイズの小さいA6サイズの台紙が使われています。電子車検証の右側には、ICタグが貼り付けられているのが大きな特徴です。ICタグには、これまでの車検証に記載されていたさまざまな情報が格納されています。
初めに導入されたのは、2023年1月の普通車向け電子車検証です。現在電子車検証を所持していない方も、次の車検から電子車検証が発行されます。2024年1月からは軽自動車も電子車検証へと移行しました。
普通車・軽自動車どちらも電子車検証導入から日が浅いことから、自動車検査証記録事項も車検証と同時に発行されます。ICタグに格納された情報は、車検証閲覧アプリまたは、自動車検査証記録事項から確認が可能です。
有効期限は分かる?車検証の見方を項目別に紹介

車検証には、有効期限以外にも番号、日付などさまざまな情報が記載されています。中には車の運用に関わる重要な情報もあるため、どのような情報が確認できるのか、見方を把握しておきましょう。
ここでは、車検証の記載内容を項目別に紹介します。新たに登場した電子車検証は見方が異なるため、しっかりチェックしましょう。
自動車登録番号や車両番号
自動車登録番号は、文字と数字で構成される識別番号です。車1台につきひとつずつ割り当てられており、文字と数字全てが同じ番号は現存しません。
同じ番号が記されているナンバープレートでも確認可能です。自動車登録番号では、登録している運輸支局や車の種別分類番号といった情報が確認できます。
登録年月日/交付年月日
「登録年月日/交付年月日」の欄には車検証の交付年月日が記載されています。
新規で登録した場合は「登録年月日」が、車の情報が更新された場合は「交付年月日」が適用されることを覚えておきましょう。この日付は、ナンバープレートが付けられた日と同一の日です。
初度登録年月・初度検査年月
初度登録年月は、普通車の新車時の新規登録を受けた年月です。初度検査年月は軽自動車の新車時の初度検査を受けた年月を表します。車の年式を表すものでもあり、売却時の査定額にも関わる重要な項目です。
新車の場合は初度登録年月・初度検査年月と登録年月日は同じになりますが、名義や住所の変更があった場合は日付が更新されます。中古車は名義が変更されるので、初度登録年月・初度検査年月と登録年月日が異なる点に注意しましょう。
自家用・事業用
車がどのような用途で使用されているのかが記載されている項目です。自家用と事業用に分かれており、ナンバープレートのカラーデザインに違いがあります。
自家用普通自動車は白いプレートに緑字、事業用普通自動車は緑のプレートに白字でナンバーが記載されるため、視覚的にひと目で判断が可能です。軽自動車の場合は、自家用車は黄色のプレートに黒字、事業用は黒いプレートに黄色い文字で記載されます。
自動車の種別
総重量やエンジンの排気量、乗車定員などによって、大型自動車・大型特殊自動車・普通自動車・軽自動車といった種別に分けられます。
例えば、軽自動車に分類されるのは総排気量0.66L・長さ3.4m・幅1.48m・高さ2m以下の車です。種別によって納税額が変わるため、所有している車がどの種別に該当するのかしっかり把握しておきましょう。
車名・車台番号・型式
車名の欄には車のメーカー名が記載されます。カローラやアクアといった車種名ではなく、トヨタなどのメーカー名が記載されるため注意しましょう。
車台番号の欄には、登録された車の固有の識別番号が記載されています。車台番号は車本体にも刻印されており、車の登録や車検を受ける際に必要です。型式は車の種別やモデル名を示しており、アルファベットと数字で構成されています。
総排気量や定格出力
車に搭載されているエンジンの排気量が記載してある欄です。単位はL(リットル)で表記されており、5.7Lであれば排気量5,700ccのエンジンであることを示しています。
電気自動車や燃料電池車はモーターの定格出力が表記されており、単位はkW(キロワット)です。
所有者の氏名や住所
車の所有者として登録している人の氏名・住所が記載されている項目です。車をローンで購入している場合は、ローン会社やディーラーなどの名称・住所が所有者欄に記載されています。
使用者欄には車を使用する人の名前・住所が記載されますが、親名義で購入した場合などは所有者と使用者の名前や住所が異なることもあるでしょう。
電子車検証には、所有者情報や使用者の住所は記載されていません。確認するにはICタグの読み取りが必要です。
有効期間の満了日
有効期間の満了日とは、車検が切れるタイミングのことです。この期日を過ぎると公道は走行できなくなるため、車検証に記載された満了日までに車検を受ける必要があります。
これまで使われてきたA4サイズの車検証には、有効期間の満了日が記載されていますが、新しく登場した電子車検証には有効期限が記載されていません。
電子車検証で有効期限を確認するには、「車検証閲覧アプリ」を使います。ICタグを読み取れないときは、ICリーダーの用意が必要です。
有効期限切れに注意!見方が分かった車検証を使うタイミング

車検証は、保安基準に適合した車であることを証明するものです。それと同時に車検証の有効期限を確認できる書類でもあります。
しかし、車検証を使う機会は有効期限を確認するときだけではありません。ここでは、車検証が必要になる4つのタイミングを確認しましょう。
住所変更するとき
引っ越しなどで住所に変更があったときは、変更登録と呼ばれる手続きが必要です。変更登録は、ナンバープレートの地域を管轄する運輸支局もしくは軽自動車検査協会で行います。
手続きの際には、車検証の他に申請書・住民票・手数料などが必要です。住所変更によって管轄が変わる場合は、ナンバープレートを交換することとなり、別途ナンバープレート代もかかります。
自動車保険に加入するとき
車を購入する際、自賠責保険とは別に任意保険と呼ばれる自動車保険に加入する方が多いでしょう。任意保険加入時には、車検証に記載された情報を入力する必要があるため、車検証を用意するとスムーズに手続きできます。
具体的に聞かれる内容は、車両型式・登録番号・使用者名・所有者名・車名・初度登録年月(初度検査年月)です。これらの情報は、加入者を識別する重要な情報であることから、申し込み時には間違いのないよう伝えましょう。
車を手放すとき
車を売却する際は、車検証に記載された名義を変える必要があります。所有者が自分名義ではない場合、そのままでは売却できないため事前に自分名義への変更が必要です。
ディーラーでローンを組み、所有権がディーラー名義になっているのであれば、所有権解除をしてもらいましょう。
車検切れの車を売却する際も同じく、車検証が必要です。車検の有効期限が切れていても、車検証が見当たらないときには再発行手続きをしましょう。
車検の更新を行うとき
2年ごとに受ける車検(継続検査)でも、所有している車検証を使用します。有効な車検証がなければ車検が受けられないことから、車検当日までに準備が必要です。車検時には車検証の他、点検整備記録簿・自賠責保険証明書・自動車納税証明書も提出します。
車検証と同じく、これらの書類がない場合は再発行手続きが必要のため、前もってそろえられるか確認しましょう。紛失を防ぐために、車検証と一緒に保管するのがおすすめです。
有効期限内の車検証を紛失したときは?

車検証は道路運送車両法によって車内に携帯することが義務付けられており、不携帯は50万円以下の罰金が科されます。もし車検証を紛失してしまったら、速やかに再発行の手続きを行いましょう。
ここでは、再発行の手続きを行う場所と、必要な書類について解説します。
再発行できる場所
普通自動車の車検証再発行の手続きを行う場所は、住んでいる地域を管轄する運輸支局です。必要書類をそろえて窓口で手続きを行いましょう。代理人が申請を行う場合は委任状が必要です。
軽自動車の手続きは軽自動車検査協会で行います。申請書に必要事項を記入し、必要なものがそろっていることを確認して窓口に提出しましょう。
再発行に必要な書類
普通自動車の車検証を再発行するために必要な書類は以下の通りです。手続きの際には手数料350円も持参しましょう。
・自動車検査証再交付申請書:運輸支局の窓口で入手できる他、運輸支局のWebサイトからのダウンロードも可能
・車検証:紛失ではなく破損の場合に必要
・理由書:紛失の場合に必要
・身分証明書:運転免許証やパスポートなどの氏名・住所・顔写真が確認できる書類
・使用者の委任状:代理人申請の場合に必要
軽自動車の車検証を再発行するときにも申請手数料として350円請求されるため、用意しておきましょう。再発行に必要な書類は以下の通りです。
・自動車検査証再交付申請書:軽自動車検査協会窓口からの入手、もしくは軽自動車検査協会のWebサイトからダウンロード可能
・車検証:紛失ではなく破損の場合に必要
・申請依頼書:代理人申請の場合に必要
ICタグが破損したときも再発行が必要
これまでの紙の車検証とは異なり、電子車検証裏面にはICタグが内蔵されています。ICタグは切り離すと車検証が無効になり、破損すると情報が読み取れなくなるため注意が必要です。
万が一、ICタグ部分を破損させてしまった場合は、管轄の運輸支局にて再発行手続きを行います。手数料がかかる他、再発行手続きの手間もかかることから、ICタグを破損しないよう適切な保管方法を心がけましょう。
有効期間内の車検証を保管するときのポイント

大切な車検証の紛失を防ぐには、決まった場所に保管することが大切です。しかし、車検証は運転時に原本の携帯が義務付けられていることから、自宅への保管はできません。ここでは、車検証のおすすめの保管場所、保管時の注意点を紹介します。
グローブボックスなどに保管する
車検証は運転時に携帯することが義務付けられています。どこに置けばよいか迷った際には、グローブボックスの使用が便利です。グローブボックスに保管すると決めておけば、提示を求められた際にもすぐに取り出せます。
「大切な書類であれば原本は自宅で保管したい」と思う方もいるでしょう。しかし、車検証は原本を携帯する必要があり、コピーでは不携帯と判断されます。車検証を受け取ったら、すぐに車内に保管しましょう。
水ぬれ対策をしておく
グローブボックスの大きさ、ふたの有無などは車種によって異なります。ふたがないと雨天時にドアを開けた際、雨が入り込むこともあるでしょう。グローブボックスに車検証をそのまま入れると、雨でぬれる可能性もあります。
車検証は紙でできていることから、雨などの水ぬれは避けたほうが無難です。チャック付きビニール袋に入れたり、車検証ケースを使ったりして、水ぬれ対策をしておきましょう。
また電子車検証はICタグ内蔵のため、電子レンジで乾燥させようとすると発火、破損の恐れがあることから使えません。
有効期限が車検証以外で分かる車検ステッカーの見方

車検に合格すると、車検証と一緒に車検標章と呼ばれる車検ステッカーが発行されます。車検ステッカーからも、車検の有効期限は確認が可能です。公道を走行する車であれば車検ステッカーは貼られているため、自分の車で確認しましょう。
ここでは、車検ステッカーの貼り方と剥がし方、有効期限のチェック方法を紹介します。
車検ステッカーの見方
車外から見えるステッカーの表面には、車検の有効期間が切れる時期が記載されています。
大きな数字は月、小さな数字は年(和暦)を表しており、この日付までに次の車検を受けなければなりません。ステッカーの色は軽自動車は黄色、軽自動車以外は青色で区別されているのが特徴です。
裏面にも車検の有効期間が満了する日が記されていますが、こちらは「○○年○月○日」と詳細な日付まで記載されています。具体的な期日を知りたいときは裏面を参照しましょう。
車検ステッカーを貼る方法
ステッカーは2つのシールを組み合わせるため、順番を間違えないように注意しましょう。
まず、色の付いたシールを中央付近まで剥がし、台紙中央にある折り目に沿って山折りします。色の付いたシールの台紙と透明なシールの台紙の中間にある線に沿って谷折りすることで、透明なシールの上部に色の付いたシールが重なる仕組みです。
ステッカーは貼る位置も決められています。前方からだけでなく、運転席からも確認しやすい位置に貼らなければなりません。着色されているフロントガラスの場合は、着色部分の下に貼ります。
車検ステッカーを剥がす方法
車検ステッカーを剥がす際には、スクレーパーを使います。スクレーパーがない場合は金属製のもので無理に剥がすのではなく、爪を使ってゆっくりと剥がしましょう。
剥がした後にガラスに粘着面が残ることがあるので、水でぬらしたティッシュとラップをかけて蒸らします。少し時間を置いてからスクレーパーやウェットティッシュなどでこすって拭き取り、ガラス面がきれいになったら完了です。
まとめ

Aタイプ、Bタイプと呼ばれる紙の車検証には、車検の有効期限が記載されていますが、2023年1月(軽自動車は2024年1月)から発行されるICタグ内蔵の電子車検証には記載されていません。
電子車検証の情報を読み取るには、「車検証閲覧アプリ」を使用します。
車検証は、車検時だけでなく売却時や保険加入時などさまざまな場面で使用する重要な書類です。破損、紛失すれば再発行する必要があるため、水ぬれ対策をしてグローブボックスに保管しましょう。
▼ライタープロフィール

畠山達也
自動車Webライター
自動車免許のほか、一級自動車整備士、フォークリフト運転免許などを保有するライター。自動車メーカーや部品業界に携わった際の知識や経験を活かし、Webメディアを通して「車の楽しさ」を発信している。
豊富なラインアップのネクステージ中古車情報をチェック!
いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。
ネクステージでは、他店に負けない数多くの中古車をラインアップしていますので、中古車の購入を検討されている方は、ネクステージの公式Webサイト上で最新の在庫状況をチェックしてみてください。また中古車購入に際して、ネクステージ独自の保証もご準備しております。お気軽にお問い合わせください。


