自動車税環境性能割の計算方法は?車を選ぶ際のポイントも解説!

車に課される税金にはさまざまなものがあり、自動車税環境性能割もそのひとつです。自動車税環境性能割は「燃費性能」に応じて税率が決まり、普通自動車・軽自動車だけでなく、新車・中古車どちらも対象となります。
車の燃費性能によって支払う税額が変わるため、どのように計算するのか知りたいという方もいるでしょう。
この記事では、自動車税環境性能割の概要と計算方法、支払うタイミングを解説します。自動車税環境性能割の負担を抑えられる中古車の選び方も紹介しますので、購入費用の削減に役立つでしょう。
※目次※
・自動車税環境性能割は自動車取得税に代わり導入された燃費性能によって課税される税金。
・自動車税環境性能割の税率は車の燃費性能によって変わり、電気自動車などのエコカーは非課税。
・車には継続的に支払う税金もあるため、維持する上でどのくらいの税金がかかるかの考慮も大切。
自動車税環境性能割が導入された経緯

自動車税環境性能割が導入されたのは、2019年10月1日です。車の税金の中でも比較的新しいもののため、10年以上前から車に乗っている方にはなじみの薄い言葉かもしれません。
自動車税環境性能割は、それまで支払う必要のあった「自動車取得税」と入れ替わる形で導入されました。はじめに、自動車取得税の廃止と自動車税環境性能割の導入の経緯を紹介します。
2019年10月に自動車取得税を廃止
自動車取得税は、50万円以上の特殊自動車を除く普通・小型自動車と、三輪以上の軽自動車を取得した人に課されていた地方税です。
新車か中古車かによって税率が異なり、年式の違いによっても課税額が異なりました。
この自動車取得税は2019年10月に廃止されています。
以前から車の購入時に消費税と自動車取得税が二重課税されることに疑問の声が上がっており、消費税が8%に増税されたときに自動車取得税が減税されました。そして、消費税が10%に増税されたタイミングで廃止されています。
自動車は高額な買い物のため、消費者にとっては消費税の増税分だけでも大きな負担です。しかし、自動車取得税が廃止されたことで税金の負担が軽減されています。
代わりに自動車税環境性能割を導入
自動車取得税が廃止されると同時に、自動車税環境性能割が導入されました。自動車税環境性能割は、車の燃費性能によって課税される新しい制度です。燃費が優れた車ほど税率が軽減される特徴があります。
税率は変動性のため、燃費性能が良い車ほど税金の負担が軽くなります。反対に、燃費の悪い車や古い車は環境に良くないという点から「重課税」対象です。
自動車税環境性能割の税額の計算は難しい?

自動車税環境性能割の税額は「燃費性能から見た税率」と「車の取得価額」によって決まるため、自動車税や重量税のように税額を瞬時に判断できません。
購入予定の車にどのくらいの税金がかかるかを知るには、燃費性能別に設定された税率を確認しましょう。ここでは、燃費性能別の税率を2つの期間に分けて紹介します。
2024年1月1日~2025年3月31日までに取得した場合
自動車税環境性能割の税率は「省エネ法の燃費基準値の達成度」により変わります。一方、新車・中古車、普通車・軽自動車共に同じ税率が使用されます。
【自家用エコカーの税率】
|
車種 |
税率 |
|
・燃料電池車を含む電気自動車 ・天然ガス自動車 (2018年排出ガス基準適合、または2009年排出ガス基準NOx10%以上低減) ・プラグインハイブリッド車 |
非課税 |
エコカーに該当する自動車(天然ガス車のみ一定の基準あり)は、環境に優しいことから非課税です。
【自家用ガソリン車・ハイブリッド車の税率】
ガソリン車とハイブリッド車は、まず「2018年排出ガス基準50%低減」または「2005年排出ガス基準75%低減」、かつ「2020年度燃費基準」を達成している必要があります。
|
条件 |
税率 |
|
2030年度燃費基準95%達成 |
非課税 |
|
2030年度燃費基準90%達成 |
|
|
2030年度燃費基準85%達成 |
|
|
2030年度燃費基準80%達成 |
1% |
|
2030年度燃費基準75%達成 |
2% |
|
2030年度燃費基準70%達成 |
|
|
2030年度燃費基準60%達成 |
3% |
|
上記以外 |
【自家用クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)の税率】
クリーンディーゼル車は、まず「2018年排出ガス基準適合」または「2009年排出ガス基準適合」、かつ「2020年度燃費基準」を達成している必要があります。
|
条件 |
税率 |
|
2030年度燃費基準95%達成 |
非課税 |
|
2030年度燃費基準90%達成 |
|
|
2030年度燃費基準85%達成 |
|
|
2030年度燃費基準80%達成 |
1% |
|
2030年度燃費基準75%達成 |
2% |
|
2030年度燃費基準70%達成 |
|
|
2030年度燃費基準60%達成 |
3% |
|
上記以外 |
2025年1月1日~2026年3月31日までに取得した場合
2025年1月1日以降に購入した車に関しては、2025年3月31日までに取得した場合よりも条件が厳しくなります。
【自家用エコカーの税率】
|
車種 |
税率 |
|
・燃料電池車を含む電気自動車 ・天然ガス自動車 (2018年排出ガス基準適合、または2009年排出ガス基準NOx10%以上低減) ・プラグインハイブリッド車 |
非課税 |
【自家用ガソリン車・ハイブリッド車の税率】
「2018年排出ガス基準50%低減」または「2005年排出ガス基準75%低減」、かつ「2020年度燃費基準達成」に関しては、2024年1月1日~2025年3月31日までと変わりありません。
|
条件 |
税率 |
|
2030年度燃費基準95%達成 |
非課税 |
|
2030年度燃費基準90%達成 |
1% |
|
2030年度燃費基準85%達成 |
|
|
2030年度燃費基準80%達成 |
2% |
|
2030年度燃費基準75%達成 |
|
|
2030年度燃費基準70%達成 |
3% |
|
2030年度燃費基準60%達成 |
|
|
上記以外 |
【自家用クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)の税率】
「2018年排出ガス基準適合」または「2009年排出ガス基準適合」、かつ「2020年度燃費基準達成」に関しては、2024年1月1日~2025年3月31日までと変わりありません。
|
条件 |
税率 |
|
2030年度燃費基準95%達成 |
非課税 |
|
2030年度燃費基準90%達成 |
1% |
|
2030年度燃費基準85%達成 |
|
|
2030年度燃費基準80%達成 |
2% |
|
2030年度燃費基準75%達成 |
|
|
2030年度燃費基準70%達成 |
3% |
|
2030年度燃費基準60%達成 |
|
|
上記以外 |
自動車税環境性能割の税額を計算してみよう

環境性能割は、車の取得価額にそれぞれの税率を掛けて税額を算出します。取得価額を誤ると金額が大きく変わるため、何を取得価額とするのかをしっかりと理解しておきましょう。ここでは、新車と中古車それぞれの環境割の計算方法を解説します。
新車を購入した場合
新車の場合の自動車税環境性能割の計算方法は、取得価額を「課税標準基準額+オプションの価額」として考えるのがポイントです。
課税標準基準額は車種やグレードを基準にして、おおよそ新車価格の9割程度の額になります。そのため、本来の価値より安く新車を購入できたとしても取得価額は変わりません。「いくらで買ったか」ではなく「車の価値はいくらか」で考える方式です。
オプションの価額は「車の購入時に付加したオプション装備の価格」を指します。新車購入時にカーステレオやカーナビなどを追加した場合は、それらの総額を車両本体価格にプラスして計算しましょう。
以上を加味して自動車税環境性能割の税額の計算方法「取得価額×自動車税環境性能割の税率」に当てはめると、新車を購入した場合は「(課税標準基準額+オプションの価格)×自動車税環境性能割の税率」で算出できます。
中古車を購入した場合
中古車の場合は、取得価額を「課税標準基準額×残価率」で算出します。残価率とは中古車の経過年数に合わせた掛け率を指し、新車購入時を1.0として時間がたつほど掛け率が下がっていく仕組みです。
1年で0.681になり、1.5年では0.561、2年で0.464になります。その後も0.5年ごとに下がっていき、6年目の0.100が下限です。
軽自動車は登録車とは掛け率が異なり、1年で0.464、1.5年後は0.316に下がります。 その後は2.5年で0.146になり、3年の0.1が下限です。登録車と軽自動車の残価率は、以下の表でご確認ください。
|
|
1年 |
1.5年 |
2年 |
2.5年 |
3年 |
3.5年 |
4年 |
4.5年 |
5年 |
5.5年 |
6年 |
|
登録車の残価率 |
0.681 |
0.561 |
0.464 |
0.382 |
0.316 |
0.261 |
0.215 |
0.177 |
0.146 |
0.121 |
0.100 |
|
軽自動車の残価率 |
0.464 |
0.316 |
0.215 |
0.146 |
0.100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
これらを考慮して自動車税環境性能割の税額の計算方法「取得価額×自動車税環境性能割の税率」に当てはめると、中古車を購入した場合は「(課税標準基準額×残価率)×自動車税環境性能割の税率」の計算で求められます。
なお、中古車の取得価額が50万円未満の場合は非課税です。50万円未満の中古車はそれほど多くありませんが、年式が古く走行距離の長い車であれば対象になる確率が上がります。
自動車税環境性能割の計算に含むのはどの部品まで?

環境性能割の計算に使う「取得価額」は、簡単にいうと「取引価格」です。この取引価格には、車の本体価格の他にオプションなどの「付加物」も含まれます。
しかし、一部の付加物は取得価額に含まれないため、どこまでが含まれるのかを理解しておきましょう。ここでは、環境性能割の計算に含められる付加物と含められない付加物を紹介します。
付加物は自動車税環境性能割の課税対象
自動車に取り付けられる付加物は、自動車税環境性能割の課税対象となります。基本的には自動車の取り付け用品を指し、その定義は「ボルトやネジによって車に固定されているもの」です。そのため、付加物に当たるかどうかを事前に見極める必要があります。
自動車の取り付け用品には「メーカーオプション」と「ディーラーオプション」がありますが、オプションの種類は関係ありません。次の項目では、付加物に含まれるものと含まれないものを紹介します。
付加物の対象となるもの
付加物の対象となるものは以下の装備です。
・カーナビ
・モニター
・リアカメラ、バックカメラ
・エアコン
・ETC車載器
・カーディオ
・スピーカー
・エアバッグ
・サンバイザー
・泥よけ
・ミラー類
・ルーフラック
ここで挙げているのは、あくまでも一例です。他にも、自動車に固定され車体と一体化しているものであれば、付加物に分類されます。これらの取り付け用品は、自動車税環境性能割の課税対象となるため注意しましょう。
付加物の対象とはならないもの
付加物の対象にならないものは以下の装備です。
・シートカバーのようなカバー類
・フロアマットのようなマット類
・ヘッドレスト
・チャイルドシート
・スペアタイヤ
・洗車用具
これらに共通するのは、車に固定されていないものであることです。例えば、フロアマットのようなマット類は、必要がなければすぐに剥がして別の場所に保管できます。チャイルドシートも、座席に固定されているわけではありません。
このように「車体に固定されているかどうか」に注目すれば、付加物の対象になるかどうかが判別できます。
計算した自動車税環境性能割を支払うタイミングはいつ?

自動車税環境性能割は自動車税や重量税とは違い、一定期間ごとに支払う必要のない税金です。税金と聞くと納付書が自宅に届き、指定された期日までにコンビニや金融機関で支払うというイメージがあるかもしれませんが、納付書が送られてくることも基本的にありません。
ここでは、自動車税環境性能割を支払うタイミングを紹介します。
購入するタイミングで支払う
自動車税環境性能割は自動車を取得した際に課税されるため、車を購入するときに購入費用と合わせて支払います。ディーラーや中古車販売店で購入した場合は、注文書などに記載されているのが一般的です。
購入時に支払うため、自動車税環境性能割の税額が高い車ほど購入金額も高くなります。とはいえ、車の購入金額は「車両本体価格」が多くを占めるため、自動車税環境性能割が高いとしても大きく影響しません。
状況によっては減免されるケースもある
自動車税環境性能割の減免措置は、基本的に「燃費性能」と「取得価額が50万円以下の場合」です。しかし、以下のような場合は減免措置を受けられます。
・障がい者手帳などの交付を受けている方が使用する車
・障がい者の方と生計を共にする方が車を所有し、通学・通院・介護のために使用する車
多くの自治体では、取得価額300万円に相当する税額を減免するとしています。減免措置の内容は都道府県で異なり、減免の申請期間も設けられているため、車の購入を考え始めると同時に減免措置の内容を確認しておきましょう。
また、相続により取得した車については、自動車税環境性能割が非課税となります。(2024年6月時点の情報です)
自動車税環境性能割の特性を生かす中古車の選び方

自動車税環境性能割の税率は新車と中古車で変わらないため、価格の安い中古車を選ぶことで支払う税金を抑えられます。しかし、取得価額が50万円以下でない限りは非課税にならないため、税率に関係する「燃費性能」も重視しましょう。
ここでは、自動車税環境性能割の税率を下げられる中古車の選び方を紹介します。
燃費性能が優れている車を選ぶ
自動車税環境性能割が優遇されるのは、電気自動車・プラグインハイブリッド車のような「エコカー」です。しかし、これらは給電が必要になるため、居住環境によっては購入の選択肢に入らないこともあるでしょう。
非課税にはならないものの、燃費性能の良いハイブリッド車やガソリン車、ディーゼル車は税率が低く設定されています。燃費性能の良い車はガソリン代も抑えられるため、維持費の面でもお得です。
ガソリン車とハイブリッド車のある車種であればハイブリッド車を選ぶ、ガソリン車しかないのであれば燃費達成度を確認するなどし、できるだけ燃費性能に優れた車を選ぶようにしましょう。
高年式のものを選ぶ
基準を達成しているか否かで税率が変わる税制のため、高年式車のほうが基準達成率は高い傾向にあります。年式の新しい車を中心に、基準を達成している車を探すのが良いでしょう。
「燃費基準達成車」と書かれている緑のステッカーや、「低排出ガス車」と書かれた青のステッカーが目印になります。
車に課せられる税金は自動車税環境性能割以外にもある
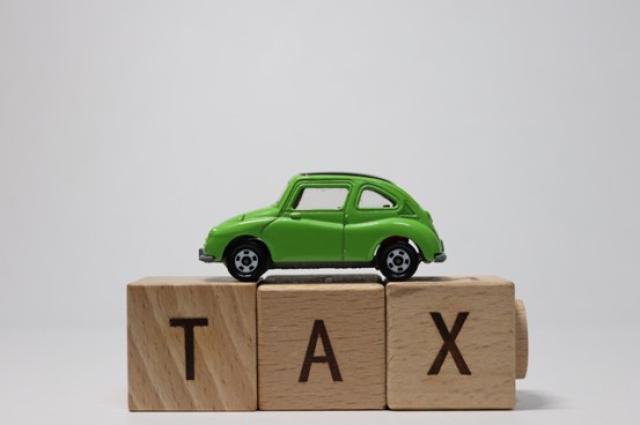
自動車税環境性能割は購入費用に影響する税金のため、少しでも安くしたいと思うでしょう。しかし、車に関する税金は自動車税環境性能割以外にも複数あります。
また、多くは所有する限り継続的に支払う必要があるため、自動車税環境性能割以上に考慮が必要です。ここでは、車に課せられる税金を紹介します。
自動車税種別割・軽自動車税種別割
「自動車税種別割」と「軽自動車税種別割」は、自動車を所有する人に課せられる税金です。
自動車税種別割は小型自動車・普通自動車に適用され、税額は排気量ごとに設定ます。軽自動車税種別割は軽自動車のみに適用され、税額は排気量関係なく一律です。
どちらも毎年4月1日時点の所有者に課され、多くの自治体が5月末日を納付期日としています。税額の決め方以外で異なるのは、自動車税種別割が「都道府県税」であるのに対し、軽自動車税は「市区町村税」であることです。
自動車重量税
「自動車重量税」は、車両重量に応じて課される国税です。小型自動車・普通自動車は500kgごとの段階に分かれていますが、軽自動車は自動車税と同じように一律の金額が設定されています。
自動車重量税は「車検ごとに納める」ため、課税されるタイミングは自動車税のように統一されていません。また、車検ごとに納めることから自家用乗用車は新車購入時に「3年分」、それ以降は「2年分」をまとめて支払います。
消費税
「消費税」は、製品や商品の購入、サービスを受けるなどの取引にかかる税金です。消費税には「標準税率(10%)」と「軽減税率(8%)」があり、車の購入では「標準税率」が適用されます。
消費税の大きな特徴は、国税と地方税で構成されていることです。標準税率の場合、10%のうち7.8%は国に、残りの2.2%は地方へ納められます。
一般消費者だけが支払う税金というイメージもありますが、法人や課税事業者の個人事業主も消費税を納めなくてはなりません。事業者が消費税を納めるのは、決算時や確定申告時です。(2024年6月時点の情報です)
ガソリン税・軽油引取税
「ガソリン税(揮発油税)」と「軽油引取税」は、どちらも燃料に関する税金です。ガソリン税はガソリンにかかる税金を指し、揮発油の製造者が国に納めます。
一方の軽油引取税は、軽油にかかる税金です。軽油の特約業者や元売り業者から軽油を購入した人が支払い、業者が都道府県に納めます。
ガソリンスタンドで支払う燃料代の中にはそれぞれの税金が含まれており、ガゾリン税は1L当たり48.6円、軽油引取税は1L当たり32.1円です。(2024年6月時点の情報です)
まとめ

自動車税環境性能割は、燃費性能によって課税される税金です。税率は該当する車の燃費性能によって変わりますが、新車や中古車による違いはありません。自動車税環境性能割の税額を計算するには、購入する車の取得価額が必要です。
取得価額は付加物によっても変わるため、詳しい税額は販売店に確認することをおすすめします。
自動車税環境性能割を少しでも安くしたいという方は、燃費性能の高い車を選びましょう。燃費性能が高い車を選ぶことでガソリン代も節約できるため、税金を抑える以外の恩恵も受けられます。
▼ライタープロフィール

中村浩紀 なかむらひろき
クルマ記事に特化したライター
現在4台の車を所有(アルファード・プリウス・レクサスUX・コペン)。クルマ系のメディアでさまざまなジャンルの記事を執筆し、2024年1月までに300記事以上の実績をもっている。
豊富なラインアップのネクステージ中古車情報をチェック!
いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。
ネクステージでは、他店に負けない数多くの中古車をラインアップしていますので、中古車の購入を検討されている方は、ネクステージの公式Webサイト上で最新の在庫状況をチェックしてみてください。また中古車購入に際して、ネクステージ独自の保証もご準備しております。お気軽にお問い合わせください。


